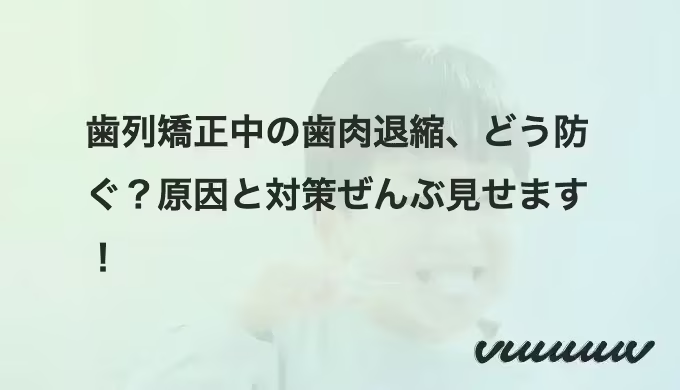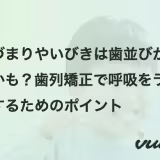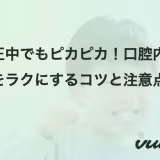はじめに|「歯茎が下がるかも…」と不安なあなたへ!
こんにちは!23歳の歯科衛生士の私も矯正治療の真っ最中。歯肉退縮(歯茎が下がる現象)は見た目にも健康にも影響があるのでドキドキしますよね。でも大丈夫!正しい知識とセルフケアでリスクを減らせます。この記事では原因・リスク・予防策・もし起きたときの対処法まで、たっぷり解説していきます!
歯肉退縮ってどんな状態?
歯肉退縮とは、歯を包む歯茎が上方向(歯冠側)へ縮んで歯根が露出し、知覚過敏や見た目の変化を招く状態です。矯正治療が直接の原因になることもあれば、もともとの歯周病やブラッシング圧の掛け過ぎなど複数の因子が重なって進行するケースも珍しくありません。実際、多くの矯正歯科がリスクとして明記しています。
なぜ矯正で歯茎が下がるの?メカニズムを徹底解説
歯の移動方向と骨の厚み
歯は骨の代謝バランスを利用して動かします。特に下顎前歯部は唇側骨板が薄く、外側へ傾斜移動させると骨が再生しきれず歯肉退縮が生じやすいとされています。
矯正装置がもたらす清掃性の低下
ブラケットやワイヤー、ゴムなどが付くと歯磨き難易度は急上昇!プラークが溜まれば歯周炎が進み、歯肉退縮を助長します。
装置の刺激と口内炎
頬や唇に当たる装置の刺激で小さな傷ができると、炎症反応が続き歯肉がやせる例も報告されています。
歯肉退縮が起こりやすい人の特徴
- もともと歯茎が薄い・幅が狭い
- 矯正前から中等度以上の歯周病がある
- 喫煙習慣がある(血流が低下)
- ブラッシング圧が強いor硬い歯ブラシを使用
- 歯ぎしり・食いしばりが強い
リスクを最小限に!セルフケア&プロフェッショナルケア
矯正前の歯周精査はマスト!
虫歯・歯周病は「先に治してから矯正」が鉄則。スタート時点の健康度で歯肉退縮リスクが大きく変わります。
毎日のブラッシング+補助清掃
歯ブラシと歯間ブラシ・フロスを併用し、プラークを徹底除去。サイズが合わない器具や力任せの清掃は逆効果なので要注意です。
定期メンテナンスとチーム医療
矯正医・歯周専門医・歯科衛生士が連携し、動的治療中から保定期までモニタリングを行うことで重度の退縮を防ぎます。
歯肉退縮が起きたらどうする?
露出歯根への知覚過敏処置、歯肉移植や矯正再治療により歯列を再配列して歯茎に厚みを持たせる方法など多彩な選択肢があります。症状・原因に応じて歯周外科を検討するケースも。
手術適応や治療効果は個人差があります。「絶対に元通りになる」「必ず改善する」とは言い切れない点をご理解ください。(医療広告ガイドライン配慮)
呼吸にも影響?歯列と気道の深い関係
歯列の幅や顎の位置は上気道の断面積に関与するといわれ、歯列矯正が睡眠時無呼吸症候群の補助治療になる可能性が報告されています。矯正目的が違っても「噛み合わせ+呼吸」が注目される時代ですね!
At Appalachian Orthodontics, Dr. Black specializes in treating obstructive sleep apnea as a Diplomate of the American Academy of Dental Sleep Medicine—the same principles we use in orthodontics can also open airways for better sleep! 😴🦷
— Appalachian Orthodontics Of Lynchburg (@AppOrthoOfBurg) March 4 2025
治療の流れと歯肉ケアのポイント
今日からできるセルフチェックリスト
| チェック項目 | 理想的な状態 |
|---|---|
| 歯ブラシ交換頻度 | 1か月に1回以上 |
| ブラッシング圧 | 毛先が広がらない強さ |
| フロス・歯間ブラシ利用率 | 毎晩100% |
| 定期検診間隔 | 3〜6か月 |
| 喫煙本数 | 0本 |
 銀座で働く現役歯科衛生士の木村さん
銀座で働く現役歯科衛生士の木村さん
矯正治療にまつわるその他のリスクもチェック
- 個人差はあるが痛み・違和感を感じる場合がある
- 装置の擦過で口内炎ができやすい
- 清掃不良で虫歯・歯周病リスクが上昇
- 保定を怠ると後戻りの可能性
- 一部装置は完成物薬機法対象外で副作用救済制度の対象外
まとめ|歯肉退縮は「予防と早期対応」がカギ!
歯列矯正は長期的な口腔健康投資。歯肉退縮のリスクをゼロにすることは難しくても、正しい知識とセルフケア、プロのサポートで限りなく小さくできます。この記事が明日からのケアのヒントになれば嬉しいです!
よくある質問
矯正前に歯周病があったら必ず治さないとダメ?
はい。活動性の歯周病が残ったままだと治療中に歯肉退縮が急速に進むリスクがあります。先に歯周治療を完了し、炎症をコントロールしてから矯正を開始しましょう。
マウスピース矯正なら歯肉退縮が起きにくい?
装置が取り外せて清掃性は高いものの、歯の傾斜量や装着時間が不十分だと退縮リスクはゼロではありません。大事なのは歯周評価と装着時間の厳守です。
歯肉退縮が起きたら矯正を中断すべき?
症状の程度によります。軽度で炎症がなければ経過観察しつつ進めることもありますが、中等度以上・痛みを伴う場合は治療計画を再評価します。歯周専門医と相談しましょう。
知覚過敏用の歯磨き粉だけで改善できますか?
一時的な症状緩和は期待できますが、根本的には歯肉退縮の進行要因(ブラッシング圧や歯周病)を改善しないと再発しやすいです。
保定装置をサボると歯茎にも影響しますか?
後戻りで歯が再度動くと骨のリモデリングが起きるため、歯肉ラインも不安定になります。リテーナーは指示どおり装着しましょう。