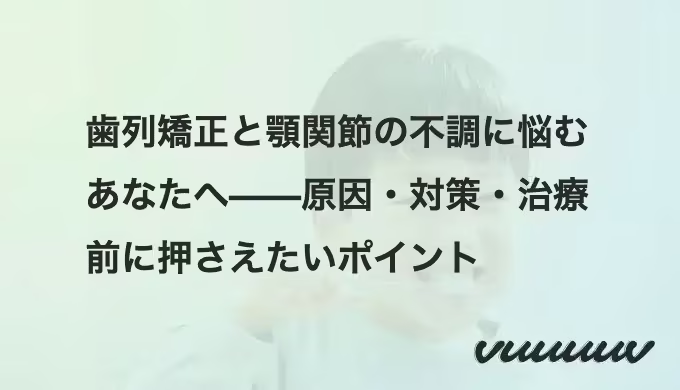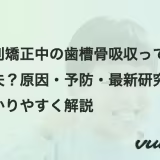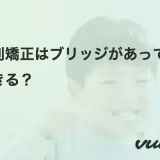顎関節はどんな働きをしているの?
上下のあごを結び、食べる・話す・あくびをするなど日常の動きを支えてくれるのが顎関節です。ボールジョイントのような構造で、関節円板・筋肉・靭帯が複雑に協調しながらスムーズな開閉運動を実現しています。日本顎関節学会がまとめた最新の指針でも、病態分類の多様さと診断の大切さが強調されています。
顎関節症(TMD)の代表的な症状
- 口を開けると関節がカクッと鳴る
- 開口時に痛みや引っかかりを感じる
- 朝起きたとき頬の筋肉がだるい
- 噛みしめ・歯ぎしりが多いと言われる
歯列矯正と顎関節異常の関連は?
「矯正すれば顎関節症が治る」「逆に悪化する」という真逆の体験談がネットに溢れています。結論から言うと、“症状の改善も悪化もどちらも起こり得る”というのが近年の臨床研究が示すところです。2023年のシステマティックレビューでは、矯正治療経験者のTMD発症オッズ比が1.84と報告され、統計的な関連が示唆されました。ただし研究デザインや対象年齢にばらつきがあり、必ずしも因果関係を断定できるわけではありません。
改善方向に働くケース
不正咬合や下顎後退がTMDの主因だった場合、咬合の安定で痛みや開口障害が軽くなることがあります!
悪化方向に働くケース
急激な歯の移動・咬合高径の大きな変化・セルフケア不足などが重なると、関節や筋にストレスがかかり症状が誘発されることも。計画とモニタリングの質がカギです。
治療開始前に絶対チェックしたい6項目
- 顎関節の既往歴と現在症状を詳しく共有
- CTやセファロだけでなくMRI撮影の必要性を確認
- 関節円板の状態を歯科医師と一緒に読み解く
- ブラキシズム・姿勢・ストレスなど生活習慣の聞き取り
- 複数の矯正装置候補と関節負荷の説明を受ける
- 治療後の保定計画とフォロー体制を把握
装置別の特徴と顎関節への負担比較
| 装置 | 特徴 | 顎関節への主な影響 |
|---|---|---|
| マルチブラケット | 細かな三次元コントロールが可 | 咬合高径変化が大きいと違和感増 |
| セルフライゲーション | 摩擦抵抗が低い | 比較的弱い力で移動でき痛みが少なめ |
| マウスピース矯正 | 取り外し可能・審美性◎ | 咀嚼時の咬合が間接的になる点に注意 |
| 機能的矯正装置 | 成長期の骨格誘導 | 関節位置を前方に誘導するため適応吟味 |
矯正治療に伴うリスクと副作用
痛み・装置による口内炎・清掃難易度の上昇・後戻りリスク・完成物薬機法対象外装置の使用など、個人差があります。処方箋外装置の場合、医薬品副作用被害救済制度の補償対象外になることも覚えておきましょう。
治療の一般的な流れ
セルフケア&生活習慣で顎関節を守る
▽ 姿勢改善やストレッチで首肩の緊張をほぐし、咬筋の過緊張を和らげる!
▽ カフェイン・アルコールの過剰摂取はブラキシズムを助長する可能性があるので控えめに。
▽ 就寝時に横向きに丸まる姿勢が多い人は、関節を圧迫しない高め枕を検討してみましょう。
最新トピック——デジタル技術が可能にする精密診断
AIセファロ解析やバーチャル咬合シミュレーションなどのデジタルツールが、顎関節評価をサポートする時代へと進化しています。
関連ポストをチェック!
上顎拡大で気道が広がったら睡眠時無呼吸が軽減!歯列矯正って見た目だけじゃないんだなあと実感🥹
— 天使 (@tenshicos) March 3, 2025
まとめ
顎関節の状態と歯列の改善、両方を目指すには“診断の質”と“継続的なモニタリング”が不可欠!不安なことは遠慮せず歯科医師へ質問し、自分のペースで進めていきましょう。
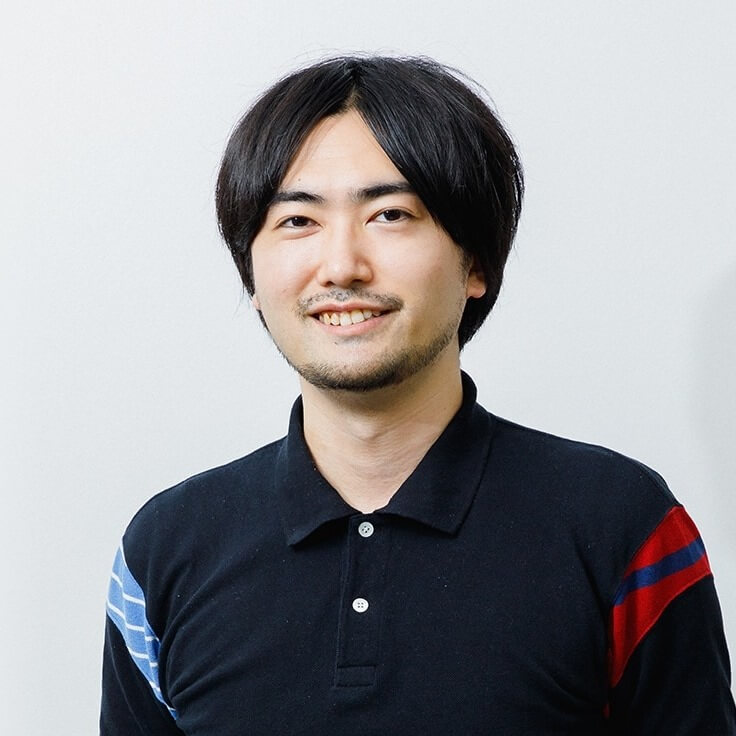 この記事の筆者
この記事の筆者
矯正中に顎関節が痛くなったらすぐ装置を外すべき?
痛みが強い場合は装置調整の中断や鎮痛対策が必要ですが、多くは一時的な炎症です。必ず担当医に連絡し、自己判断で装置を外さないようにしましょう。
保険が使えるケースはある?
唇顎口蓋裂や顎変形症など厚労省が定める疾患が原因の場合など、限られた条件下で適用されます。届出医療機関でのみ対応可能です。
マウスピース矯正は顎関節に優しい?
弱い連続力が特徴ですが、装着時間が不足すると咬合が不安定になり逆に負担が増える例も。装着管理と定期チェックが大切です。
顎関節症があると矯正は受けられない?
受けられないわけではありませんが、関節の安定を優先し、疼痛コントロールやスプリント療法を併用して計画を立てるのが一般的です。
矯正後に関節が再び痛くなることは?
保定装置の装着不足・姿勢やストレスの変化などで再発することがあります。定期検診と生活習慣の見直しでリスクを下げましょう。