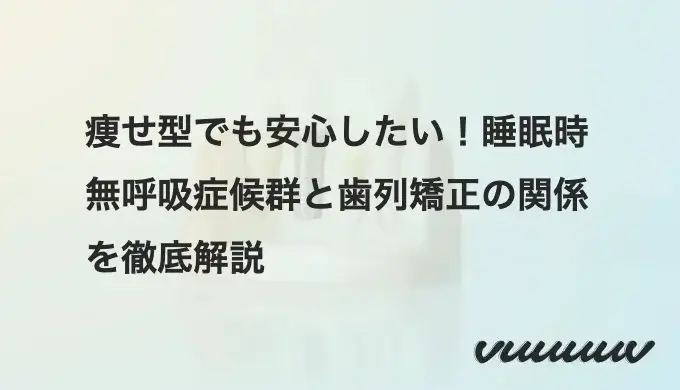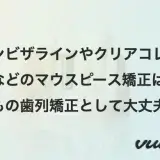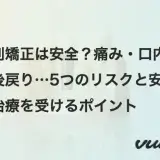痩せているのに睡眠時無呼吸症候群?歯列矯正で改善する可能性を解説!
「いびきが大きい」「日中に強い眠気が続く」のに自分は痩せ型――そんな30代以上の女性は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)でも原因が歯並びや顎骨格にあるかもしれません。本記事では「歯列矯正 無呼吸症候群」をキーワードに、骨格・歯列由来の閉塞性SASのしくみや、矯正治療が気道確保に役立つメカニズムを中立的に解説します!
痩せ型なのに無呼吸症候群?骨格・歯列が原因になるしくみ
肥満が主要因と思われがちな睡眠時無呼吸症候群ですが、日本人ではBMI25未満でも約半数がSASという報告もあります。森下駅前クリニックの記事によると、「下顎の後退」「顎が小さい」「上顎の幅が狭い」などで舌が後方へ沈下しやすく、気道(上気道)が物理的に狭窄します。その結果、仰向け睡眠時に気道が塞がり閉塞性SASを起こすのです。
顎顔面CTやセファロ(頭部X線規格写真)を用いた解析では、痩せ型SAS患者の多くがオトガイ(あご先)から頸椎までの距離が短いことが示されています。顎が小さいため舌骨と舌根が後退し、睡眠時に軟口蓋と舌根が接触しやすくなる――これが痩せ型SASの典型的パターンです。
閉塞性SASは「気道の狭窄+睡眠中の筋緊張低下」がセットで起こります。つまり、骨格的に気道が狭いだけではなく、寝ている間に筋肉がゆるむことで気道が閉じてしまうのです。
歯列矯正が気道を広げる仕組み
歯列矯正で歯列弓を拡大したり、下顎を前方誘導したりすると、舌が前に収まりやすくなり咽頭腔が広がることがわかっています。臨床的には、
- 上顎の狭窄→拡大床でアーチを広げる
- 下顎後退→機能的矯正装置や外科的矯正で前方へ
- 出っ歯→非抜歯矯正で後退量を最小限に
といったアプローチで気道容積を平均20〜30%拡大できたという報告があります。
なお、UPPP(口蓋垂軟口蓋咽頭形成術)や上下顎骨前方移動術といった外科手術は、重度症例でAHI(無呼吸低呼吸指数)の大幅改善が確認されています。ただし侵襲が大きいため、まずは矯正+CPAPやスリープスプリントといった低侵襲治療から検討するのが一般的です。
矯正装置の種類と睡眠時無呼吸への関連
| 装置 | 特徴 | 気道への影響 |
|---|---|---|
| 表側ワイヤー矯正 | ほぼ全症例に対応。細かいコントロール◎ | 非抜歯かつ歯列拡大を組み込むと気道拡大に寄与 |
| 舌側ワイヤー矯正 | 裏側に装置を付け審美性○。費用高め | 表側と同様に計画次第で気道拡大が期待 |
| マウスピース矯正 | 透明で取り外し可。軽~中等度向き | 大幅な顎前方移動は難しいが、歯列拡大で効果例あり |
| 小児成長期矯正 | 拡大床・機能的装置で顎を大きく誘導 | 将来のSASリスクを予防できる可能性大 |
| 外科矯正(顎変形症) | 手術併用。保険適用あり | 上下顎骨を前方移動→重度SASの根本改善例多数 |
この記事の筆者
矯正治療で知っておきたい10のリスク
- 装置装着初期の痛み・違和感
- 清掃性低下による虫歯・歯周病リスク
- 治療期間が延びる可能性
- 歯根吸収や歯肉退縮
- 歯の神経失活リスク
- 装置・金属アレルギー
- 顎関節への負担
- 装置破損・誤飲
- 予期せぬ計画変更
- 保定装置を怠ると後戻り
矯正治療は医薬品副作用被害救済制度の対象外となる装置もあります。十分に説明を受け、同意書を確認しましょう。
医師と相談したいチェックリスト
- 無呼吸の重症度・合併症
- 歯列・顎骨格の精密検査結果
- 矯正と他療法(CPAP・スプリント)の併用計画
- 治療期間・費用・支払方法
- 保険適用(顎変形症)の可能性
診断から矯正完了までの流れ
よくある質問(FAQ)
痩せている人でも本当に睡眠時無呼吸症候群になりますか?
はい。日本人は顎が小さい方が多く、肥満でなくても閉塞性SASを発症する例が数多く報告されています。
歯列矯正だけで無呼吸が治りますか?
顎骨格や歯列が主因なら症状軽減が期待できますが、完治を保証するものではありません。CPAPやマウスピースを併用するケースも多いです。
治療期間と費用はどれくらい?
成人全体矯正で1.5〜3年・総額80〜120万円が目安です。外科矯正は保険適用なら自己負担は大幅に軽減されます。
保険適用になる条件は?
「顎変形症」の診断で外科手術を伴う矯正治療の場合に保険適用されます。睡眠時無呼吸症候群のみでは適用になりません。
矯正後に後戻りしないためのポイントは?
リテーナー(保定装置)を指示通り装着し、定期検診を受けることです。保定期間を怠るとSASも再発しやすくなる可能性があります。
まとめ – 痩せ型でも無呼吸をあきらめない!
痩せ型の睡眠時無呼吸症候群は、歯並びや顎骨格が鍵になることも少なくありません。歯列矯正は気道確保をサポートしうる有力な選択肢ですが、他療法との組み合わせや専門医の連携が重要です。まずは睡眠科で検査を受け、原因を見極めた上で矯正を含む治療計画を立ててみてください!