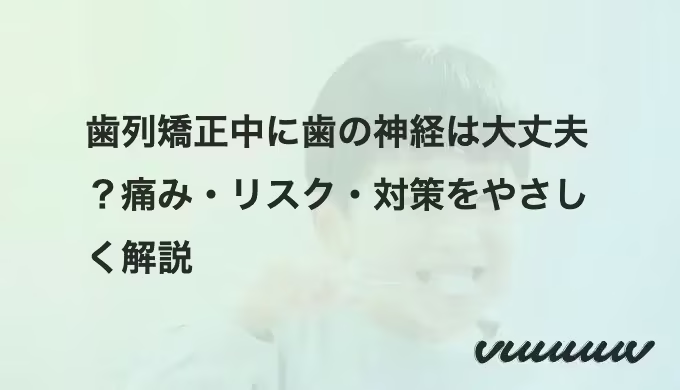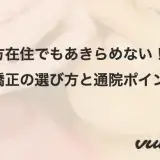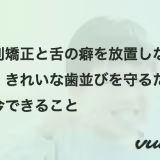歯列矯正中に歯の神経は大丈夫?痛み・リスク・対策をやさしく解説
どうして「歯の神経」が心配になるの?
「歯列矯正=歯を強い力で動かす治療」というイメージから、「神経が死んでしまうのでは?」と不安になる人は多いですよね!特にインターネットでは根管治療(歯の神経を取る治療)の経験談と矯正体験談が混在しているため、混同が起こりがちです。まず知ってほしいのは、適切な矯正力で動かせば歯髄(しずい=歯の中の神経・血管)は基本的に生き続ける、というエビデンスがあることです。
矯正力と歯髄の関係——最新研究でわかったこと
2024〜2025 年にかけて発表された系統的レビューでは「矯正力そのものが歯髄壊死を直接引き起こす可能性は低い」と結論づけられています。ただし過度に強い力や長期間かかり続ける力は微小循環を阻害し、炎症性サイトカインが増えることで歯髄に不可逆的変化を起こす危険性も示唆されています。
歯髄がダメージを受けやすいケース
- 外傷歴のある歯を動かす場合(打撲・脱臼・破折など)
- 根の成長が止まった成人歯(加齢による血流低下)
- 急速拡大装置など短期的に大きな力を加える装置
- 根管治療後すぐに矯正を始める場合(外科的侵襲の重複)
神経がダメージを受けたときのサイン
痛みや違和感が急に強くなる・歯の色が灰色〜黒っぽく変色する・温冷痛が消える、といった症状が現れたら早めに歯科医師へ相談してください。自己判断で装置を外すのはトラブル拡大の原因になります!
矯正期間中の定期的なパルプテスト(電気・温度・レーザー血流測定など)は、ダメージの早期発見に有効です。
歯の神経を守る5つのセルフケア
神経を取った歯(失活歯)でも矯正できる?
結論から言えば多くの場合で矯正は可能です!ただし根が短くなる「外部吸収」が進行している場合は、動かす方向や距離に制限が出ることがあります。下表は失活歯と生活歯の違いをまとめたものです。
| 項目 | 生活歯 | 失活歯(根管治療済) |
|---|---|---|
| 痛みの有無 | 力の調整で違和感程度 | 基本的に痛みを感じにくい |
| 根吸収リスク | 中〜高(症例による) | わずかに高い傾向 |
| 動かせる距離 | 原則制限なし | 動揺度・根長に応じて制限 |
| 装置選択 | ワイヤー・アライナーどちらも可 | 弱い連続力を出せるアライナー推奨 |
根管治療後6か月以内は歯周組織が安定していない場合があります。主治医と相談し、X線・CBCTで治癒を確認してから矯正を開始しましょう。
リアルな体験談:睡眠時無呼吸症候群と歯列矯正
顎の成長不足や口呼吸に伴う睡眠障害と矯正治療は切っても切れない関係です。最近 X(旧 Twitter) でも子どもの顎拡大と無呼吸を話題にするポストが増えています。
矯正始めて半年の経過✨ 現在小5、アデノイドあり(手術済)で 睡眠時無呼吸症候群 もあったけど、顎を広げてから夜ぐっすり眠れるようになった!呼吸って大事だね😊 #歯列矯正 #拡大装置
— ぱんだ🐼歯列矯正中 (@mike0u0mame) May 12, 2025
 銀座で働く現役歯科衛生士の木村さん
銀座で働く現役歯科衛生士の木村さん
矯正治療に伴う一般的なリスクと対策
日本矯正歯科学会の見解や厚生労働省の広告規制を踏まえ、リスクを客観的に整理します。
- 痛み・違和感:通常は数日〜1 週間で落ち着くことが多い
- 装置のこすれによる口内炎:ワックスやシリコンカバーで緩和
- 清掃性の低下:虫歯・歯周炎リスクアップ→フッ素利用+定期クリーニング
- 後戻り:保定装置(リテーナー)を指示通り装着
- 完成物薬機法対象外装置の使用:補償制度の対象外である可能性がある
よくある質問(FAQ)
矯正で歯の神経が本当に死ぬことはありますか?
適切な力と管理下では稀と考えられていますが、外傷歴など既存リスクがある場合は可能性が否定できません。症状が出たらすぐに歯科医師へ!
根管治療済みの歯は動かしても大丈夫?
動かすことは可能ですが、根長が短い場合は弱い力でゆっくり動かすなど、治療計画の調整が必要です。
アライナー矯正は神経に優しい?
複数のレビューで根吸収リスクがワイヤーより低い傾向が示唆されていますが、エビデンスの質は低めです。
睡眠時無呼吸症候群も矯正で治りますか?
顎の骨格性狭窄が原因の場合、顎拡大や外科的矯正が改善に寄与する例があります。ただし個人差が大きく、治療効果を保証するものではありません。
矯正後に保定装置を付けないとどうなる?
歯は元の位置へ戻ろうとする性質があります。特に動かした直後は後戻りしやすいため、医師が指定する期間はリテーナーを装着して安定化させましょう。
まとめ:神経を守りつつ理想の歯並びへ!
矯正治療で歯の神経が「絶対に」ダメージを受けないと言い切ることはできません。しかし、科学的な根拠に基づいた力の設定とこまめなチェック、そしてセルフケアを徹底すれば、そのリスクは大きく減らせます。心配な点は遠慮なく歯科医師・歯科衛生士へ相談しながら、一緒に笑顔あふれる歯並びを目指しましょう!